「うちの子、毎日ちゃんと勉強してくれたらな…」そんなふうに思ったこと、きっと一度や二度じゃないですよね。でも、やみくもに「勉強しなさい!」と言うだけでは、逆効果になることも。本記事では、子どもの個性を大切にしながら、楽しく自然に学習習慣を身につけていくためのヒントを7つご紹介します。どれも今日から試せるものばかり。お子さんの「やってみたい!」を引き出して、親子で笑顔になれる学びの時間を作っていきましょう。
遊び感覚で学べば、学習は「楽しい時間」になる
「勉強=つまらないもの」と思われてしまう前に、学びって実はおもしろい!と思ってもらうのがポイントです。遊びと学びをうまく融合させれば、子どもは自分からどんどんやるようになりますよ。楽しいことには自然と集中できるのが子どもの特性です。

ひらがなカルタや九九リズムで自然に覚える
学びの第一歩は、「知ってる!できた!」の積み重ね。ひらがなや九九などの基礎は、カルタやリズム遊びにしてしまえば自然と口ずさむようになります。「い〜ろ〜は〜に〜♪」なんて歌いながら覚えると、記憶にも残りやすいんです。親が一緒にやってあげるだけで、子どもは喜んでのってきます。
- ひらがなカルタを一緒に読み上げながら遊ぶ
- 九九をリズムゲーム風に言ってみる
- タイマーで「何秒で言えるか」にチャレンジ
ゲーム感覚の教材で「やらされ感」をゼロにしよう
最近は無料アプリや市販教材でも、ゲームみたいに進められるものがたくさんあります。例えば「問題に正解するとキャラクターが育つ」タイプの教材は、まるでRPGのようで子どもが夢中になります。やらされてるという感覚が薄れるので、毎日続ける習慣にもつながりますよ。


勉強っぽくないところが、逆にやる気出るらしいよ。
自然に覚えてしまうタイプの勉強法だね!

「やらなきゃ」より「やりたい」が勝ったら続けられるよね。
学習は“自分で決めたこと”にすると続きやすい
親が決めたことを一方的に押しつけると、どうしても反発したくなるのが子ども。逆に「自分で決めた」という感覚があると、びっくりするほどちゃんとやってくれることもあります。日々の学習も、ちょっとした“選択”を与えることで自主性が育ちますよ。

自分が「やりたい!」って言った方が習い事とかが続く感じありますね!

子ども自身が選ぶ「今日の学びメニュー」作戦
たとえば、国語と算数のプリントを2枚ずつ用意して「どっちをやってみる?」と聞いてみましょう。選ばせるだけで、自分で決めた感が生まれて、やる気が変わります。朝のうちに“今日の学びメニュー”を決めて、冷蔵庫に貼っておくのもおすすめです。
子どもにホワイトボードを渡して“先生役”にしよう
実は「教える側になる」と、学びの定着率ってグンと上がるんです。小さなホワイトボードを渡して「先生やってみて!」とお願いしてみてください。自分で考えて説明したり、書いたりするうちに自然と内容が身についていきますよ。

「この問題の解き方をママに教えて」って言うと、張り切るよね。

先生になった気分で、ちょっと誇らしげな顔してた!
「学ぶこと=冒険」に変える親の声かけテク
子どもって「やらなきゃダメ」って言われると、急にやる気がなくなったりしますよね。でも「今日はどんなことに挑戦する?」みたいに“冒険感”を出すだけで、ぐっと前向きになることもあるんです。親の声かけひとつで、学びはワクワクするものに変わります。

「今日のチャレンジ」などワクワク感を演出
「この問題解けたらレベルアップ!」「今日のボス問題はこれだ!」なんて言いながら取り組んでみるのも手。学習の目的を「達成感」に置き換えると、子どもは自然と前向きになります。ポイントは、ちょっとだけ背伸びすれば届くくらいの課題を選ぶこと。無理すぎてもダメ、簡単すぎてもダメ。その“ちょうどいい冒険”を仕掛けるのが、親の出番です。

「今日のチャレンジ!」って言ったら目がキラッとしてたな〜

ゲームのステージ感覚で勉強してるって感じね。
成功体験を積ませて「できた!」の積み重ねを
子どもが自信をつけるには、「できた!」という体験が何より大切。だからこそ、少しずつでもクリアできる課題を選び、「すごいじゃん!」と具体的に褒めてあげるのがコツです。たとえば、「5問解けたね!」ではなく「さっきの引き算、最後まで自分で考えられたのがすごいね」と伝えてみましょう。
- 小さなゴールをたくさん用意する
- 「できた」を記録して見える化
- 具体的な言葉で褒める
生活リズムに学習を組み込めば、続けるのが当たり前になる
毎日バタバタしがちだけど、決まった時間にほんの少しでも学習を入れておくと、習慣化しやすくなります。いきなり30分勉強しなさいって言っても、なかなか難しいですよね。だからこそ“5分だけ”から始めるのがコツなんです。

毎朝5分だけの学習タイムで集中力を引き出す
朝ごはんのあと、登校までのほんの数分。そこで1問だけ漢字を書いたり、簡単な計算をしたりするだけでOKです。朝は脳がスッキリしているので、覚えたことも残りやすいんです。「できた!」の感覚で気分よく学校へ送り出せるのも嬉しいポイント。

「朝5分って決めると、逆にやる気になるのよね〜。

短いからこそ、続くんだよね。毎朝コツコツが大事!
夜は“ふりかえり日記”で1日を振り返る習慣を
夜の5分は、今日頑張ったことや楽しかったことを一言でもいいので書く「ふりかえり日記」に。ノートや小さなメモ帳に書くだけで、1日を整理する力がつきます。学習だけじゃなく、気持ちの面でも落ち着いて一日を締めくくれるようになりますよ。
- 今日できるようになったこと
- 先生や友達に言われて嬉しかったこと
- 明日やってみたいこと
親子で一緒に取り組むことで「学習=愛着時間」に
「勉強しなさい!」って言うより、一緒に関わってみると…不思議と子どもの手が動き出すんですよね。学習を“愛着時間”に変えるコツは、親子の関わり方。たった10分でも、向き合う時間があれば、子どもは安心して学びに集中できます。

勉強中に声かけより「となりに座って一緒にやる」
「ちゃんとやってるの?」と声をかけるだけじゃなく、そっと隣に座ってみてください。それだけで、子どもは「見てもらえてる」と感じて、やる気が出るんです。わからないところがあればその場で聞けるし、何より一人じゃない安心感が大きい。

ただ座ってるだけでも「見守ってもらってる」って感じるんだよね。

干渉しすぎない距離感が、意外とちょうどいいのかも。
親も“ちょっとだけ勉強”する姿を見せるのが効果的
子どもは親の背中をよく見ています。「ママも一緒にお勉強するね」と言って、読書や家計簿、ちょっとした資格のテキストを広げるだけでもOK。勉強が“特別なこと”じゃなくて“日常の一部”だと感じさせることが、何よりの学習習慣になります。
- スマホを手放し、集中して隣にいる
- わざと手帳や本を広げて“勉強モード”を演出
- 子どもが終わったら「お疲れさま」と共感の声を
ユニークな仕掛けで“続ける工夫”を忘れない
どんなにいい勉強法でも「続かない」と意味がないんですよね。子どもが自分から続けたくなる仕掛けが、長い目で見ていちばん大事。モチベーションの火を絶やさないためには、ちょっとしたご褒美や記録の工夫が効いてきます。
「10回やったら1つシール」ご褒美式チャレンジ表
「1回やったらシール」「10回できたらお菓子」など、ご褒美チャートは子どもが喜ぶ鉄板ネタ。視覚的にも進んでる感があるから、「あと少し頑張ろう」ってなるんですよね。とくに低学年の子は、達成の見える化が効果てきめんです。


あと3回やればコンプリート!とか燃えるよね〜。
スタンプカード制で“続ける”ことに意味を持たせる
「勉強した日=スタンプ1個」にして、10個貯まったら親子でプチおやつタイム、なんてのもおすすめです。スタンプのデザインを子どもに選ばせるのも楽しいですよ。「勉強した=嬉しいことがある」という流れができれば、自然と続くようになります。
- お気に入りのキャラクターシールを用意
- スタンプ帳は子どもの手作りにして愛着アップ
- 貯まった数に応じて特別イベントを用意
場所を変えると、子どもの集中力もガラリと変わる
毎日同じ場所、同じ机で勉強していると、どうしても飽きが来てしまうもの。子どもにとっては、環境の変化そのものが刺激になります。ちょっと場所を変えるだけで「気分が変わってやる気が出た!」なんてことも珍しくありません。
週末は図書館で“特別な学習時間”を演出しよう
平日は自宅で、週末は図書館というルーティンにすると、いつもと違う雰囲気の中で新鮮な気持ちで学べます。周囲の静けさや、他の人も勉強している空気感が“集中スイッチ”を押してくれることも。親子で一緒に本を選ぶのも楽しみのひとつになります。


図書館だと自然と静かに集中できるんだよね〜。
ダイニング→リビング→ベランダ、勉強場所を旅させる
家の中でも“場所を旅する”感覚で、今日はダイニング、明日はベランダ…と変えてみるのもおすすめ。特に低学年のうちは「今日はどこでやろうか?」と声をかけるだけで、子どもはちょっとワクワクした気持ちになれます。変化は集中力の味方です。
- 気分がリフレッシュされて集中しやすくなる
- 「今日はここ!」という選択がやる気につながる
- 視覚的な刺激で学習内容の印象も変わる
【まとめ】子どもの「やりたい」を引き出すのが学習習慣の近道
結局いちばん大事なのは「子ども自身がやりたいと思えるかどうか」。そのためには、環境・声かけ・工夫をちょっとずつ取り入れていくのが効果的です。押しつけるのではなく、寄り添いながら“やりたい気持ち”を育てていきましょう。
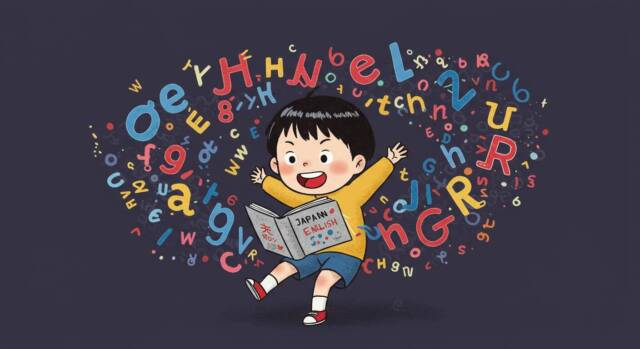
押しつけるのではなく、子どもが主役になる工夫を
勉強を「やらせるもの」ではなく、「一緒にやっていくもの」と考えることで、親子関係もスムーズになります。「どれやってみる?」「一緒にやろうか?」の声かけだけで、子どもの表情が変わることも。学習は、親子の信頼関係の延長線上にあるんです。
親が楽しんで関わると、子どもも自然と学びが好きになる
一緒に笑ったり、工夫したり。そんな時間こそが、子どもにとっての学習の土台になっていきます。「うまくいかない日があっても大丈夫」という気持ちで、ぜひ気軽に取り組んでみてくださいね。

うちも最初は全然だったけど、一緒にやってるうちに変わったなぁ。

完璧じゃなくていいよね。楽しんでる姿がいちばん伝わる!
よくある質問(Q&A)
- 子どもが机に向かいたがらないときは、どうすればいい?
-
まずは“机でやるもの”という固定観念を外してOK。リビングやベランダなど、気分が変わる場所でスタートするだけで、自然と始めやすくなることもあります。慣れてきたら少しずつ机に戻していけば大丈夫です。
- 三日坊主で終わってしまうのですが、続けるコツは?
-
「完璧に毎日やる」より、「できた日をちゃんと認める」が続けるコツです。スタンプやシール、親子の約束など小さなモチベーションを積み重ねると、自然と習慣になっていきますよ。
- 兄弟で差が出るとき、どう接すればいいですか?
-
比べるのではなく、「その子のペース」を見てあげることが大切です。兄弟で得意・不得意は当然違いますし、それぞれの頑張り方に寄り添う方が、結果的に二人とも前向きになります。










コメント